定電流負荷だと、電位が定まらず必ずどっちかにクリップします。これは相手方の抵抗値が極めて
大きいからです。
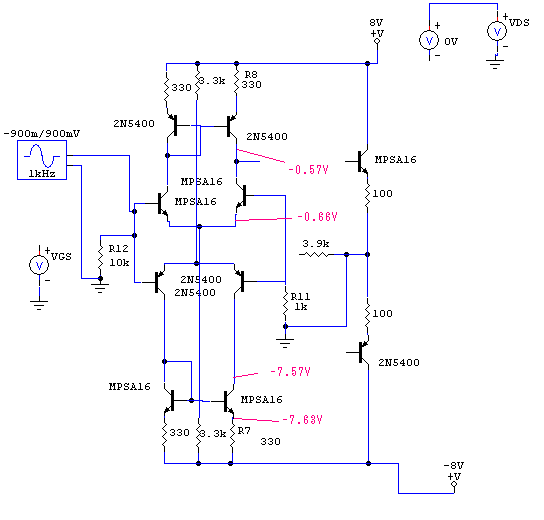
またこいういった回路は、コレクタ電位がエミッタ電位より0.6Vくらい高ければ正常動作するはずですから、
結構自由な電位で動作させることができると承知しておきます。
電位の決まり方
定電流負荷だと、電位が定まらず必ずどっちかにクリップします。これは相手方の抵抗値が極めて
大きいからです。
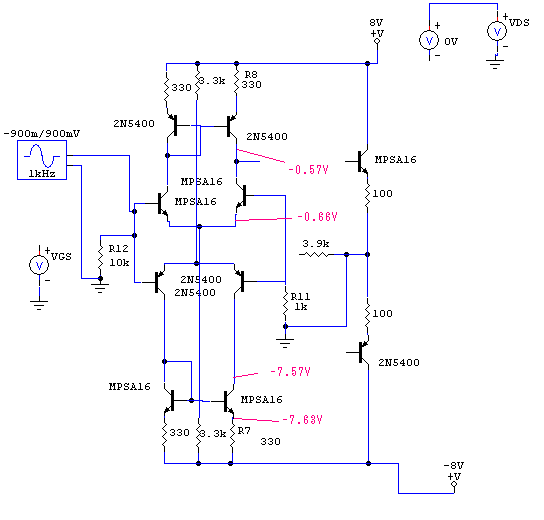
またこいういった回路は、コレクタ電位がエミッタ電位より0.6Vくらい高ければ正常動作するはずですから、
結構自由な電位で動作させることができると承知しておきます。
このように電圧源に4kをつないだものを負荷としてぶら下げてみます。
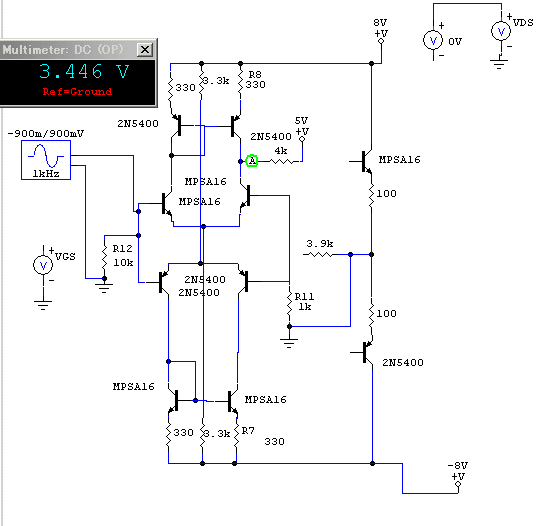
このように準電圧源をつなぐだけで、その付近の電圧に定まります。エミッタ抵抗付のトランジスタは
ベースから見て大体hfe*Rのインピーダンスの電圧源に見えるはずです。ベースの電位は、Vbe+R*Icで
決まります。
負帰還をかけてしまえば適正なIcにおさまりますから、このようになります。
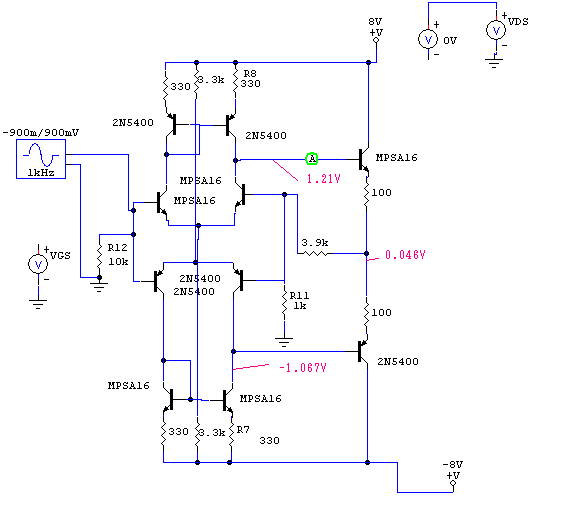
DC設計のしかた
エミッタ抵抗を100Ωとし、エミッタフォロアに流す電流を3.7mAと決めます。
赤で囲んだ抵抗を調整すれば、大体3.7mAに調整できます。
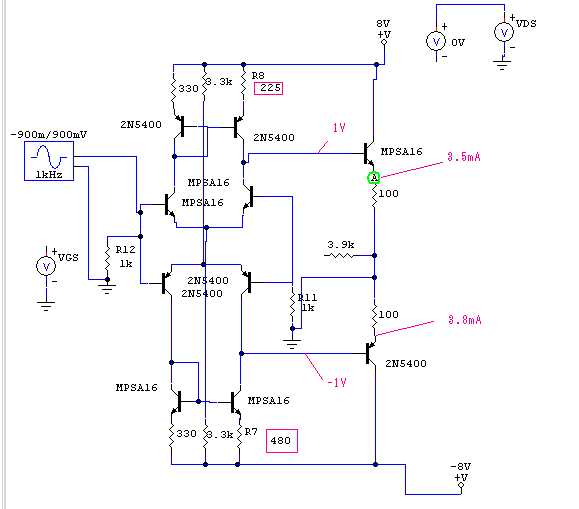
この定数で帰還をかければ、上下の電流値が揃い、オフセットも調整なしより小さくできます。
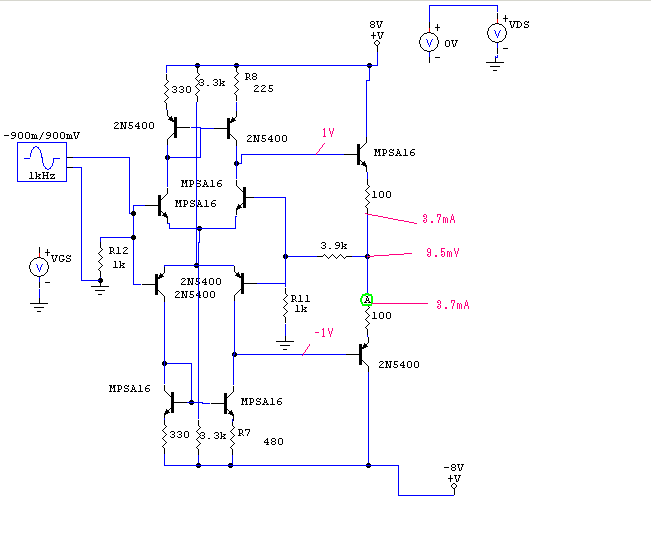
初段抵抗の変更でフォロアの電流を自由に設定できます。
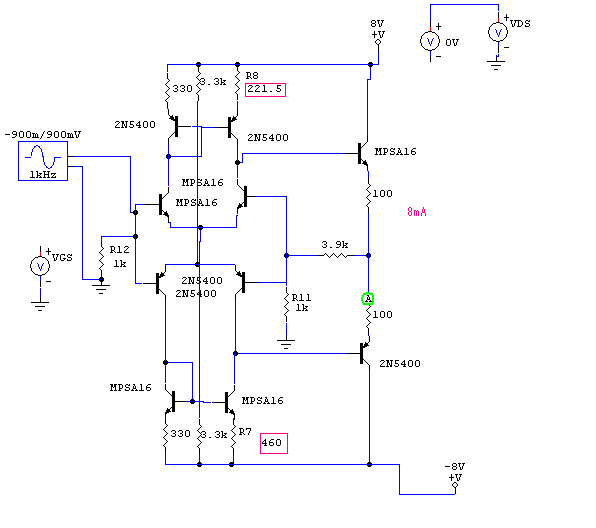
これはDCバランス優先の設計なのでACバランスはむしろ悪化していますから、初段の抵抗値を
あまり変えないところで帰還をかけたほうが良いかもしれません。
さて話は変わりますが、この回路では4VPPまで出力がとれます。
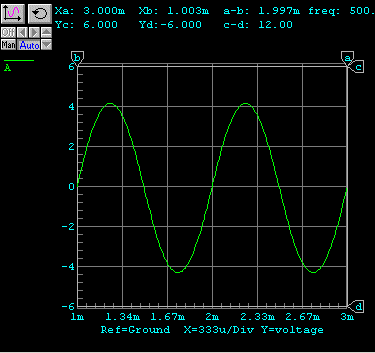
しかし、上側の電流を確認すると、完全なB級動作になっています。
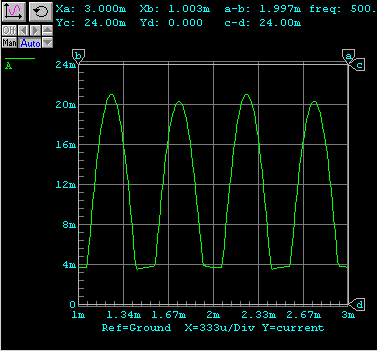
このような回路にして検討してみると、
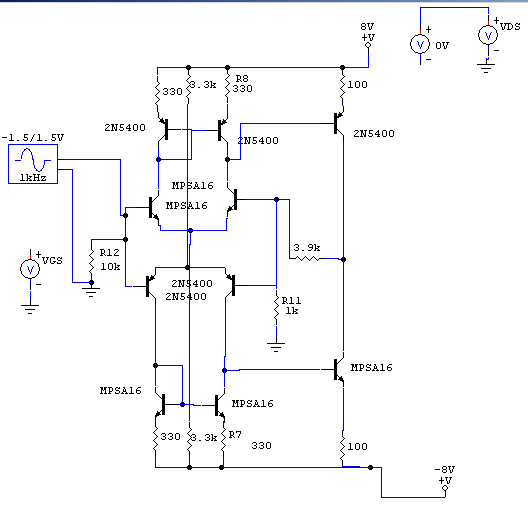
出力はほぼ電源電圧まで取れ、
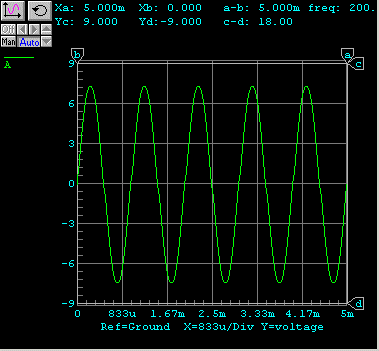
A級動作になっています。
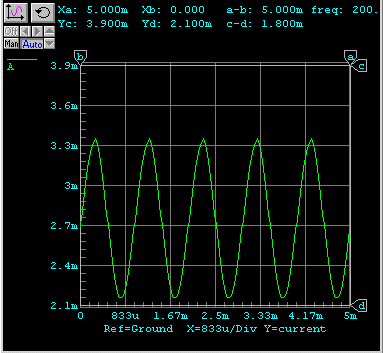
積極的に最初の回路を選択する理由は見当たりませんが、どうして最初のような回路を
発想したのでしょうか。
上の回路は正帰還になっていました。なのに正常に描画されて不思議です。
PSPICEで追試
このようなレイアウトで動かしてみました。
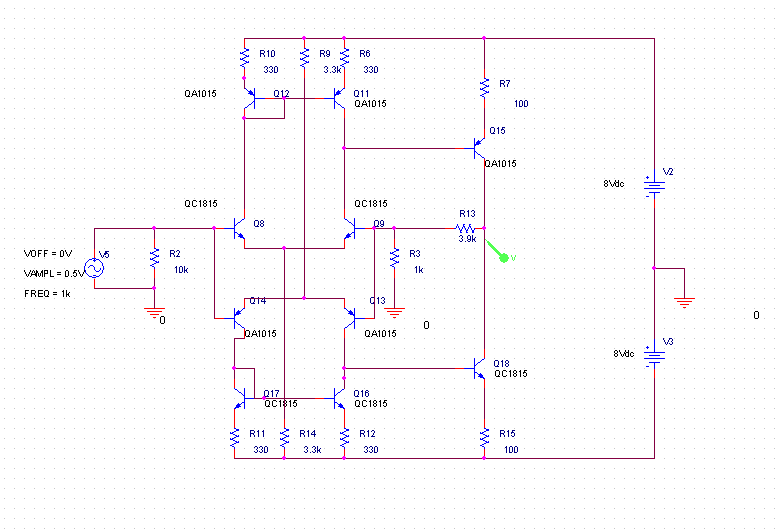
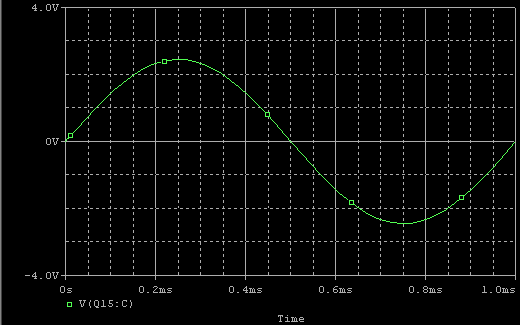
正常に動作します。
帰還をはずすとゲインの大きい反転アンプ。
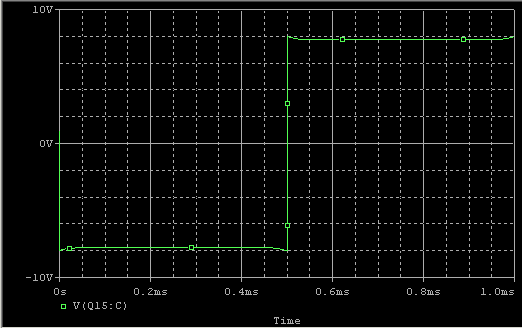
入力を小さくしました。
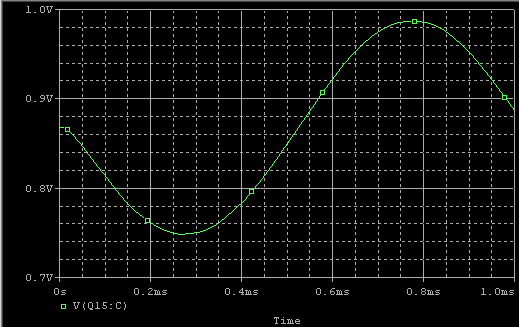
動作することはとりあえず間違いないかと思います。
DCスイープと静特性を見ました。
1段回路
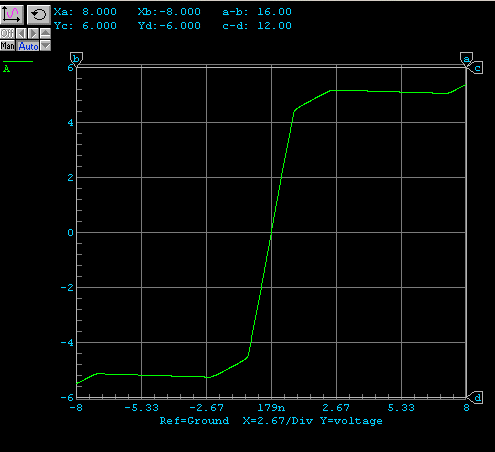
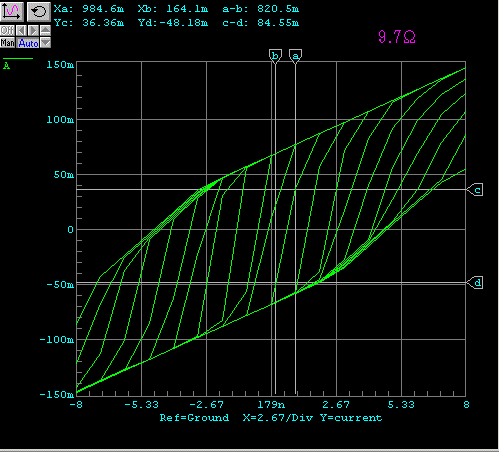
正帰還2段回路
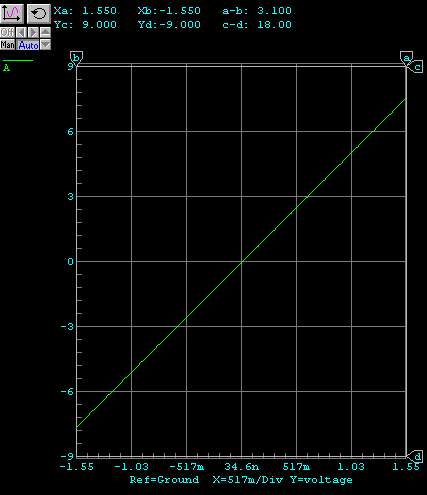
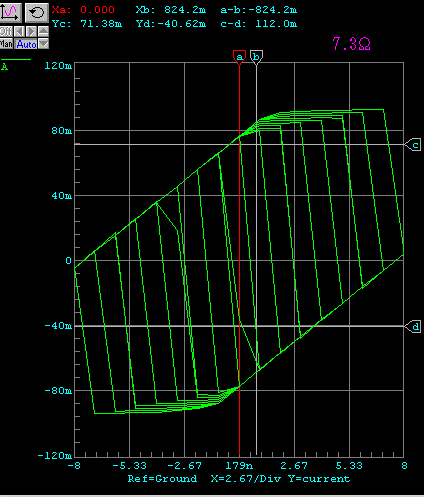
負帰還2段回路
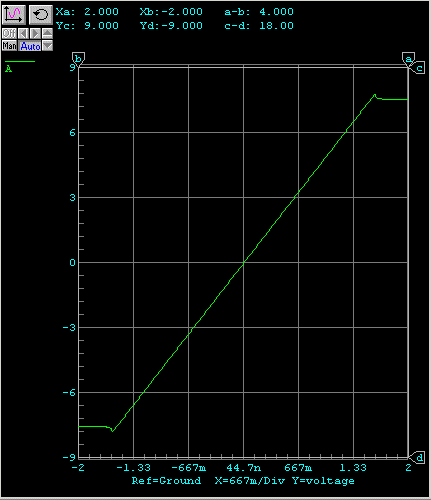
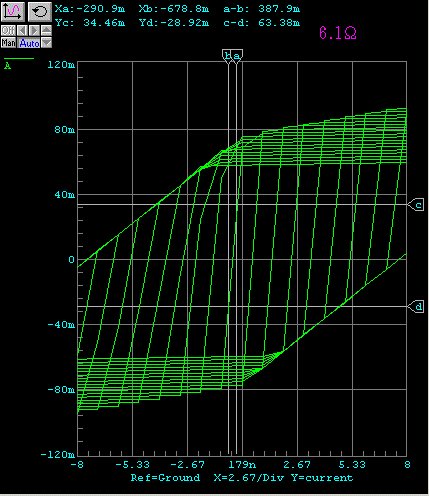
正帰還回路も入力が1.55Vを越えると発振するようです。それまでは動作するようです。
















