SRPPを論じる前に理解しておくべき基礎事項

AとBは一段増幅、Cは2段増幅ですが、電流が流れ出すところがないので上も下も同じ電流
が流れます。その結果上側は負荷抵抗と同じ動作を強いられることになります。
Dはニ段増幅の一段目と2段目がほぼ対称動作の電流合成になっています。
第1部
SRPPを論じる前に理解しておくべき基礎事項
第2部
SRPPの問題点
1 上下のゲインを揃えること
(これは比較的容易)
2 上下の出力インピーダンスを揃えること
(三極管では理論的に不可能)
3 ドライブ電流の非直線性
4 ドライブ電流の行く先
第1部
SRPPを論じる前に理解しておくべき基礎事項

AとBは一段増幅、Cは2段増幅ですが、電流が流れ出すところがないので上も下も同じ電流
が流れます。その結果上側は負荷抵抗と同じ動作を強いられることになります。
Dはニ段増幅の一段目と2段目がほぼ対称動作の電流合成になっています。
負荷線
Aの場合で見てみましょう。

まずこのような回路でプレート特性を描かせます。

負荷線をひきます。
これでよいのでしょうか?そうではありません。出力に100kΩの負荷が
ぶらさがっているわけですからもっと他の方法で考えなければなりません。
A

このポイントで電圧を振り、そこから流れ出す電流を見ます。

94.48Vのとき100kΩに流れる電流がゼロですから、そこを通るように
100kΩの傾きの直線を引きます。
B
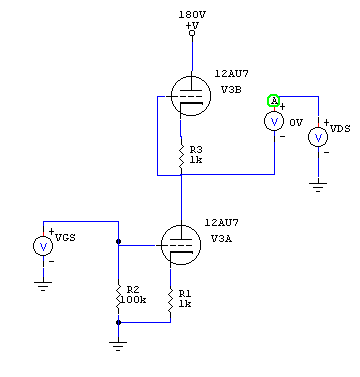

90Vをゼロポイントにして直線を引きます。AとBはほとんど同じ
特性です。
D

もうここまでくるとシミュレーターなしでは理解できない世界です。
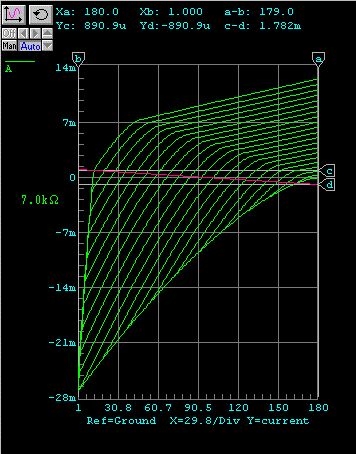
AとCを重ね合わせてみます。
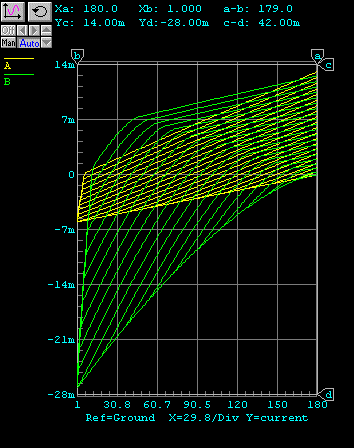
拡大して負荷線を引いてみます。

奇しくも同じ位のところを通っています。
ただこれではこの回路の低インピーダンス特性をよく利用している
とはいえないでしょう。
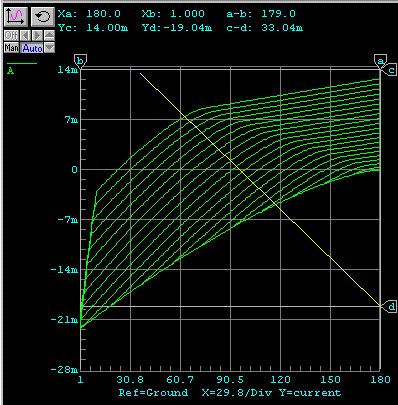
このくらいの負荷が適当です。
直結回路とC結合回路の比較
DC解析をするときは直結回路でなくてはなりませんから、上の解析は
Cをはずして第3の電源を使っています。そのへんで若干C結合と違うこと
なるので少し調べておきましょう。
100kΩ負荷



4.7kΩ負荷

三角波クリップ

正弦波

このくらいの違いが出ます。
対称動作を追求する。
このようにしてグリッド−カソード間の電位の変化をしらべます。同時に対称
に動くことがプッシュプルの要件になります。
100kΩ負荷
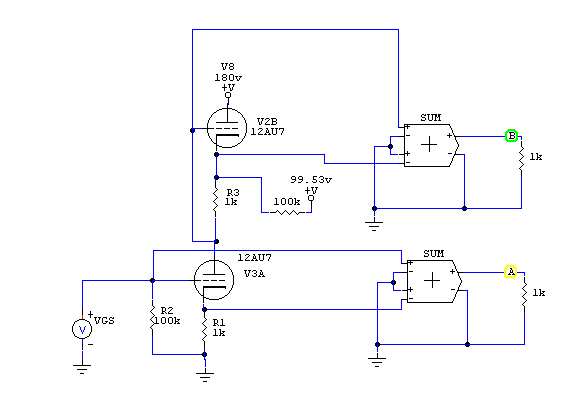
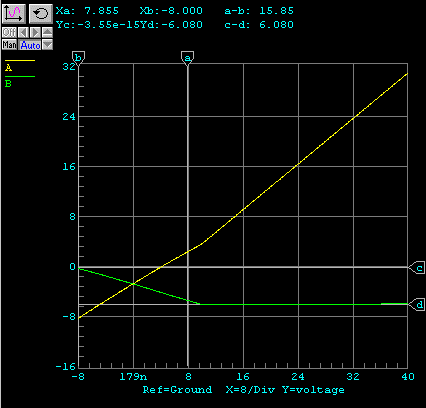
4.7kΩ負荷
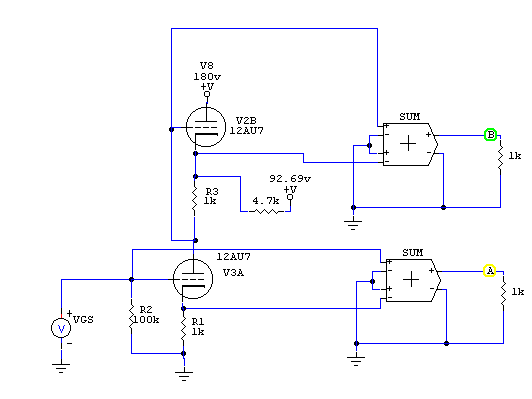
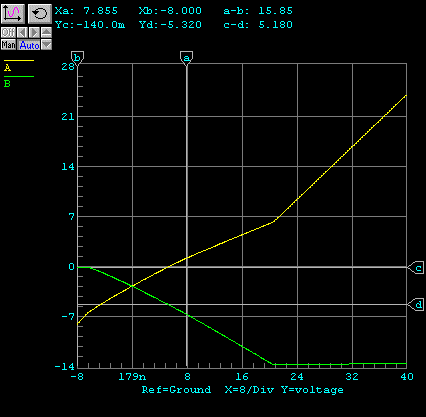
100kΩでは上側の動く範囲が少ないようです。4.7kΩではほぼ対称
に見えます。そのかわり非直線性が出てきています。
4.7kΩ負荷ではなんとか対称動作をしているようなので、その状況証拠
を検証してみましょう。

4.7kΩ負荷で三角波クリップを見てみると、

拡大します。
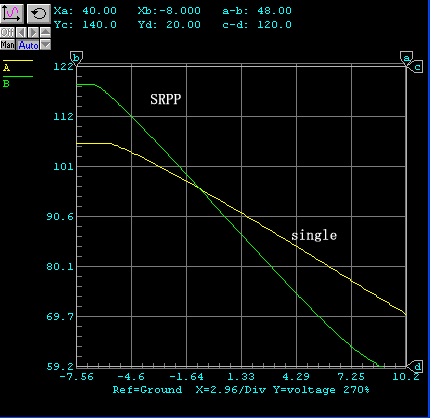
SRPPはS字カーブになっています。
シングルの方の波形を位相反転して、合成してみたのが下図です。

良く似たカーブが得られました。
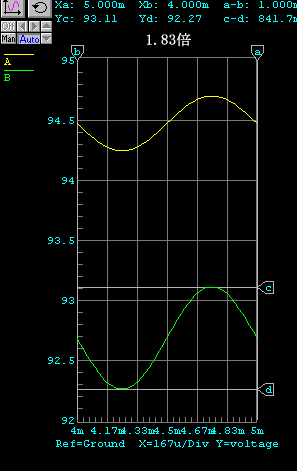
両者のゲインの差です。
100kΩではどのように調べても対称動作の痕跡はでてきません。
さきほどの図のように動作において下側の方が優勢なのがその理由であると
考えられます。
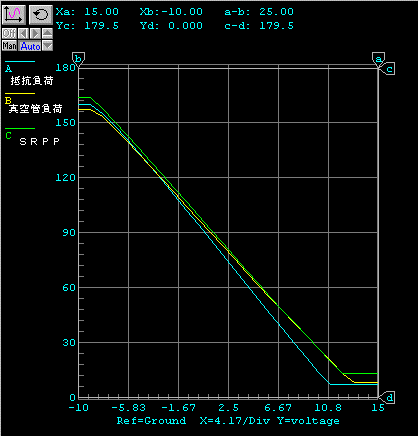
このとおり直線性はほぼ同じです。
負荷を変えてその変化を調べました。

結論

Cの回路は2段増幅の一段目と2段目の電流合成でニ段目優位状態
で、動作上シングルとの差は少ない。ただ負荷の負担が小さいので歪み
特性が良好になるかもしれない。
Dの回路は2段増幅の一段目と2段目がほぼ対称動作の電流合成であり、
奇数次歪みの打ち消し、出力インピーダンスが半分になるなどA級プッシュ
プルの特徴を備えている。これらの差異はもっぱら負荷抵抗の大きさの違
いによるものである。
第二部 はまたいずれ。
目次に戻る