例えばこのような3次関数の増幅器を調べてみる。
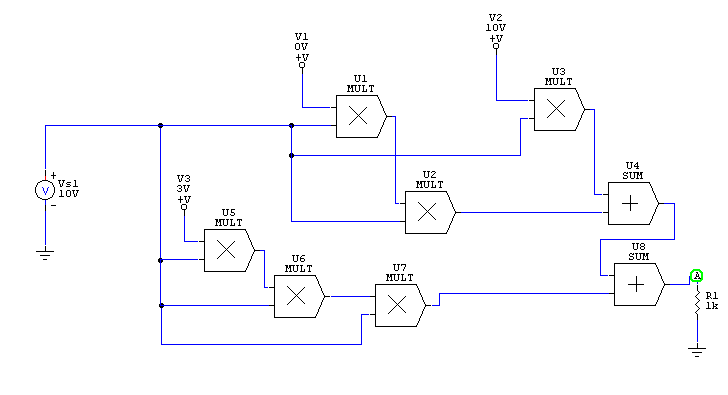
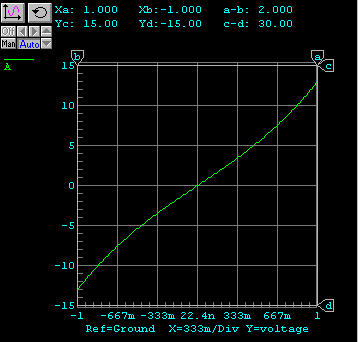
いわゆるエンハーンスメント特性である。


3次歪みが出ていた。
3次歪みについては謎が多い。
例えばこのような3次関数の増幅器を調べてみる。
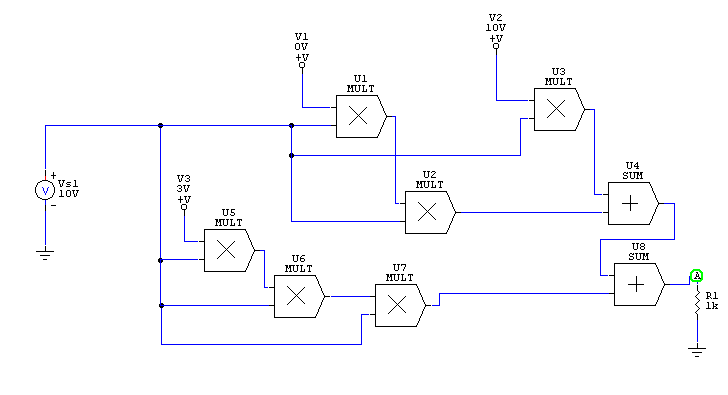
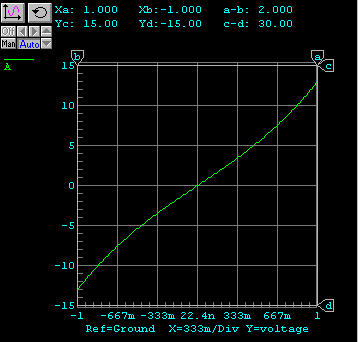
いわゆるエンハーンスメント特性である。


3次歪みが出ていた。
次にデプレッション特性の増幅器を調べてみる。
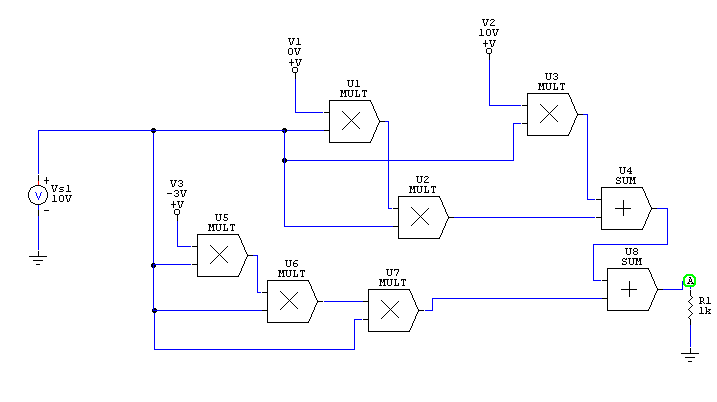

電源の制限などでよくみかける特性である。
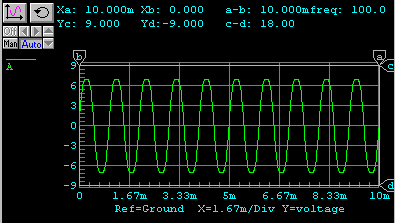
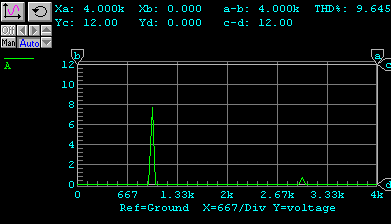
わりと歪みは少ないが、クリップすると高次の歪みが大量に出るかというとそうでもない。
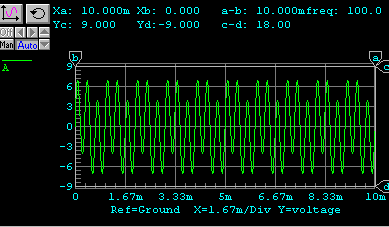
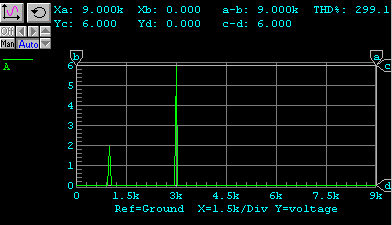
3次歪みだけである。それはそうである。
実回路ではやはり高次の歪みがでるだろう。
前にもやった歪み成分を合成して音を聴いてみようという企画です。


この比率にしたがって正弦波を合成します。

基本波と歪み成分の位相が合っているとこのようになり、
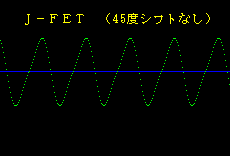
45度ずらすとこのようになります。このほうが見なれた波形です。音は?
全く同じと思います。(差がわかる人は天才かも)

3次歪みは位相があっていても大丈夫です。
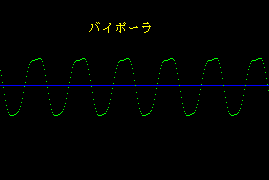
音声ファイル
1kHz正弦波 −> FET −> FET(45度シフト) −> バイポーラ
の順に再生されます。音色の感じではフルート、 オーボエ、 オーボエ、 人工的で空虚な音という風に
感じ取れます。
空虚な音の理由は基音に対して完全一三度(完全五度のオクターブ上)がいっしょに鳴っているという
和声楽上の禁止事項を犯しているからでしょう。
二次歪みの場合はいわゆるユニゾンですから、和声学的には合格なわけです。
和声楽ができた18世紀には電気は有りませんでしたが、どうやらその頃の人も3次歪みは嫌いだったの
でしょう。
45度シフトとそうでないのとの区別がつかないのは、人が波形でなくスペクトルを聴いているという
説の傍証として使えそうです。



























































