1)バイポーラトランジスタ
現在のシリコントランジスタは雑音特性、周波数特性など初期のものとくらべて
文句のつけ様がないくらいすぐれた特性をもっています。しかも値段が安い。(1本
10円から30円)
不満な点があるとすると、音がすっきりしすぎて物足りないことくらいでしょう。
2)J-FET
登場したころは、高周波特性がとびぬけて良いことから、チューナーのフロントエンド
に1石で使われていました。(ソニーのIC 11というラジオがそう)いまでは価格もさがり、
1本数10円なので、オールFETアンプも製作可能になっています。
3)V−FET
夢の素子FETでパワー段ができたら素晴らしいだろうという思いを日本の技術で可能に
したものです。ヤマハのB1がそれで、素晴らしい特性を持ち、未体験の音がでていたもの
と思われます。
4)MOS−FET
日立の技術陣が素子の開発からアンプの設計まで手がけた記念碑的なアンプが、
HMA−9500です。V−FETの弱点を見事に解消し、特性も素晴らしい素子が開発
されました。その後ラムダコンが入ったHMA−9500IIとなり、名機として君臨しました。
MOS−FETはその後も本命として発展を続けています。
5)ゲルマニウムトランジスタ
真空管とトランジスタがまだ両方使われた時代にパワー素子が登場しましたが、
高価で壊れやすく、シリコントランジスタが登場するとすぐ消えてしまいました。
しかしいまでは音質的に面白いという人もいて、ものさえあれば完全対称回路で復活
させてみたいところです。
バイアスは適正なアイドリング電流を流すために必要
C1775Aでバイアスをかける方法は、この前やったばかりですが、これは自己
バイアスと呼ばれている掛けかたです。

Vbに2Vかけると、電流が勝手に流れてVbeが約0.6Vになってくれます。
これはバイアスの自動調整機能なので、自己バイアスと呼んでいます。
さっきと話が違うって?実はこちらのほうが実情に近いのです。Vbeは常に
一定ではなくて、コレクタ電流によりわずかに変化するのです。
Vb=Vbe+Ve
Vbで示した点に2Vかけると、最初のコレクタ電流が0の状態では、Veは0V。よ
ってVbeは2Vとなりコレクタ電流は数アンペア流れようとしますが、電流が流れた
瞬間にエミッタ抵抗の電圧降下によりVeがあがり、Vbeが減少することからコレクタ
電流は急速に減少します。そして実際はちょうどよい電流のところで安定するのです。
このことをエミッタ抵抗により電流帰還がかかったというふうに呼んだりします。
これらのことを視覚的に理解するにはこのようにします。まずトランジスタの特性図を
見ると、
(本物がないので模式図です。正確な図は日立半導体のホームページを参照し
てください。)
室温25℃、Vcc=12V
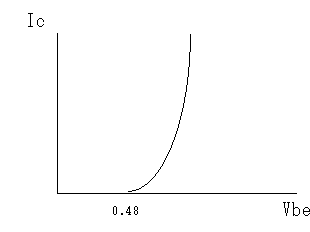
C1775Aはバイアス電圧が0.48Vから電流が立ち上がり、ほぼ指数関数
の曲線となります。
次に、Vbeと直列に抵抗がはいることから、350Ωの抵抗の特性図を書き入れ
ます。電圧の和が一定なことよりどちらかを左右反転させて書くことにします。

両者の交点がバランスする電流値です。
(1.35 : 3.8 ≒ 2 : 5.7)
解説終わり