続自作事始め
ここではどうやって電子回路について理解を深めてゆくかその方法について
書きたいと思います。
ただし充分な情報を得るにはネット上では無理ですので成書を参照するようにし
てください。
1 ニュートンの運動方程式
ma=F
このように書く理由は、実際の現象に近い発想で式を見たいからです。
ふつう質量mの物体が、加速度aで運動中であることは観測できるかも
しれませんが、加わっている力は見えません。
式の意味としては、質量mの物体が加速度aで運動していることが観測
されたとき、この物体に作用している力(ベクトル)の大きさはFであるという
様に考えます。
さてオームの法則についても同じようなことが言えると思います。
E=I*R
これは抵抗Rに電流Iが流れたときの電圧降下がEである。という風に
読みます。
これを抵抗Rに電圧EをかければIの電流が流れると読むのはあまり
おすすめしません。
理由は追ってお話しましょう。
2 回路の各部に任意の電圧を与えてみる
複雑な回路図をみたとき、これはいったいどうやって設計するのだろう
と誰しも思うに違いありません。すべての部分が関連しあって全体になって
いるからには、コンピュータを使うか天才の頭脳をもってしてやっとできるの
ではないのか?と私も思ったりしましたが、実際は電卓で四則計算すれば
おおまかな設計はできてしまいます。(慣れれば暗算でも可能です)
ヒントは抵抗による電圧の分圧にあります。これが理解できれば、回路
の任意のポイントに任意の電圧を与えることができるようになるからです。
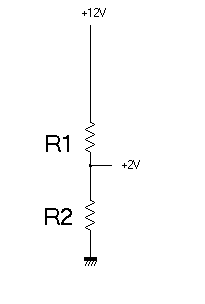
ここで2Vのバイアス電圧をつくりたければ、R1:R2=10:2に設定
すれば大丈夫です。
3 回路を縦に割ってみてゆこう
簡単な回路で実際に見てみましょう。
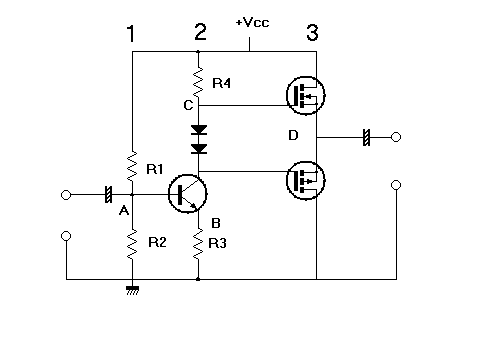
まず1のラインですが、A点の電位は電源電圧+VccをR1とR2で分圧
したものです。
次にB点ですが、トランジスタのVbe=0.6Vということを知っていれば、A点
より0.6V低いということがわかります。
B点の電位が決まれば、R3の大きさによって自由に2段目の電流値を
設定できます。(なぜならB点に現れる電圧は定電圧源とみなせるから)
4 I=E/Rを使っていいのはEが定電圧源のときだけである
ここで、I=E/Rとやってはいけない理由について考えてみましょう。
ふつうの電源の場合、抵抗Rを負荷として電流を流せば、どうなるでしょうか。
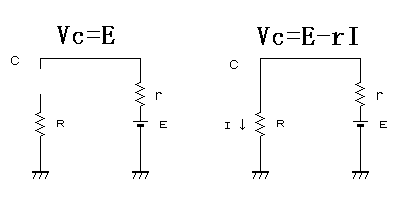
電源の内部抵抗をrとすると、流れた電流によって電源電圧が下がってしまい
ますから、C点の電位は、
E-I*r
となって電流を流す前とは違ってきてしまいます。ふつうは内部抵抗rはわかって
いないので、電流を流すまではEがどうなるかはわからないといえます。
したがってI=E/Rが成立するのは、Eが定電圧源であるときか、流す電流がじゅう
ぶん小さい場合に限るということになります。
E=I*Rとして見れば常につじつまが合います。
5 ライン2はA級増幅段である
さてここでR3を適当に決めることができますが、どういう値が良いのでしょ
うか。
それはこの部分がA級シングルアンプであることからちょうど良い値がきまってき
ます。2SC1775を使うとすれば、低歪みで使える電流の範囲はだいたい10mA
までなので、4mAに設定しておくのが適当です。そうすると入力に交流信号を加え
たときに電流が最大で0mAから8mAまで動くことになります。
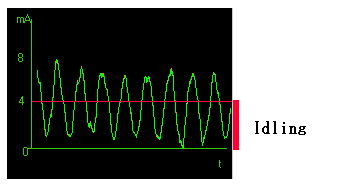
想像図
このときにR4を電源効率がもっとも良くなるように選んでおきます。
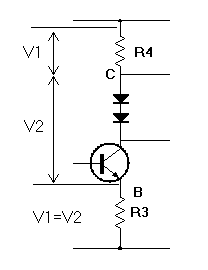
C点の電位が、VccとVeの中点にくるように設定します。
6 ライン3はB級プッシュプル段である
D点の電位はどうなるのでしょう。C点からNチャンネルFETのVgs分を引い
たものと考えられますが、ここはダイオードの電圧降下で固定されていると考えて
C点-0.6V
という様に求まります。(電圧の解析終わり)
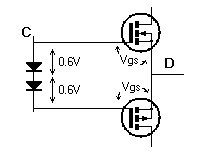
プッシュプルの話はまたの機会に。