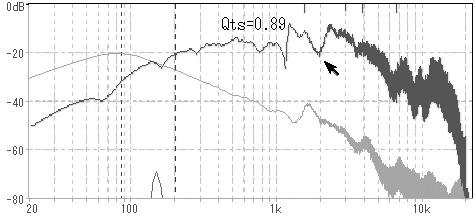振動モードを直接観察できる方法としてはホログラフィがあり、メーカー資料ではときどき
見かける。Cook Bookでもその辺は模式図の引用程度ですませてある。
コーンを伝わってエッジで反射してできる定在波の話は、音速から計算してみると分割振動と
は関係なさそうである。
(例をあげると、アルミコーン、コ−ン幅2cmの場合、音速を4800m/sとすると、定在波の周波数は
概算で240kHzくらいになると思われる。)
コーンがこのように曲がりやすいとすれば、最も単純な分割振動の様子は次の模式図のようになる。
(fig.b, fig.c)
しかしこう振動しているからといって、分割のしかたによって2次、3次高調波が発生してくるわけでは
ない。おそらく増加しているのはバネ付加による奇数次高調波だけであろう。
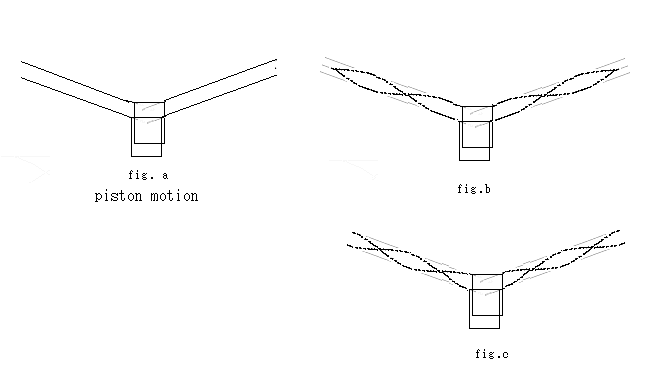
これはいわゆる同心円モードだが、同心円モードと比べ、ラジアルモードはあまり発生して
いないと思われる。テクニクスの資料をみると、特殊な肉厚のコーンを用いて、わざわざラジア
ルモードを誘導している例があるからである。
あまりに高速になると、エッジは追従しないと思われるが、1ヶ所だけエッジが反対方向に
強烈に共振する周波数がある。これがエッジの反共振周波数で、わりと低いところにあるようで
ある。

このように中域にあるので音質に与える影響は甚大である。材質や形状によりfsやQがいろいろと
違ってくる。概してゴムエッジではQが大きい。メタルコーンではfsが高い。小口径なほどfsは高い。タン
ジェンシャル・ウレタンエッジではQが小さい。などということが言える。