FE103M密閉箱で、マイクで拾った波形です。


このように低域は素直に減衰しています。
バスレフは飛び道具である
なんとなく感覚的にそう思う方もいるのではないでしょうか。
しかしバスレフを100%使いこなすには電流正帰還アンプが必要です。これが使えるようになると、
まさに飛び道具であることが体得できます。
バスレフスピーカーで起こる重要な現象
1 foc1 のQが高すぎて低音が壊れる現象
対策:Qoの低いスピーカーを用いる
2 振動版面積<<エンクロージャー外皮面積 でないとき、ダクト駆動不良が生じる。
対策:負性インピーダンスアンプを用いる
3 ダクトのチューニングが低すぎて楽音の欠落が生じる。
対策: バスレフでは帯域は欲張らない。
これらの現象を理解し対策をたててあれば、透明で豊かな音が得られます。レスポンスも
密閉よりはるかに早いです。
次に、
密閉スピーカーで起こる現象
1 Q=0.7とするとコーンの共振音がもろに出る。
対策:なるべくきれいな共振音にしておく。
2 Q=0.5以下にすると低音が全くでなくなる。
対策:ローブーストする
3 低域にゆくにしたがってキャビティ内圧による大きな歪が発生する。
対策: 速度型MFB
4 音に変換するのに振幅を必要とするので、大きなパルシブな音でコーンがもたつく現象が起こる。
対策:音楽ジャンルを選ぶ
また、バスレフが軽量コーンで良いのに対し、大面積の振動板をどうやって駆動するかという問題が
覆いかぶさります。
今回は密閉の3について例示します。
FE103M密閉箱で、マイクで拾った波形です。


このように低域は素直に減衰しています。
入力波はオフセットを持つコサイン波です。サイン波の半波ではありません。
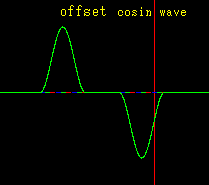
では、普通のアンプではどうなっているか見てみましょう。
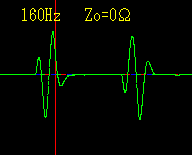



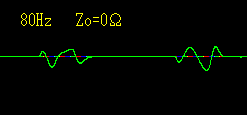

見て判るとおり2次歪みが発生している上に、前後非対称になっています。
低域にいくほど現われていることから、空気圧による歪みと推定されます。
負性インピーダンスアンプで改善されるかどうか見てみましょう。
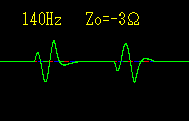

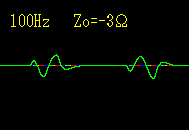

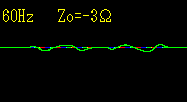
このように少ない歪みです。
この状況を4波バーストで見ておきましょう。
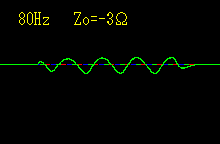

連続波ではっきりと歪みが観測されます。
電流波形を調べます。
コーンの動きが少ない最初の1波で電流が多く流れ、負性インピーダンスアンプ駆動では、
制御電圧も発生しています。電磁制動が強くかかる200Hzでは電流は激減し、低域に行くに
したがって電流が多く流れるようになります。コーンがあまり動いていないからです。

密閉で起こったことがバスレフでも起こるでしょうか?
まず密閉とバスレフのレンジの違いです。
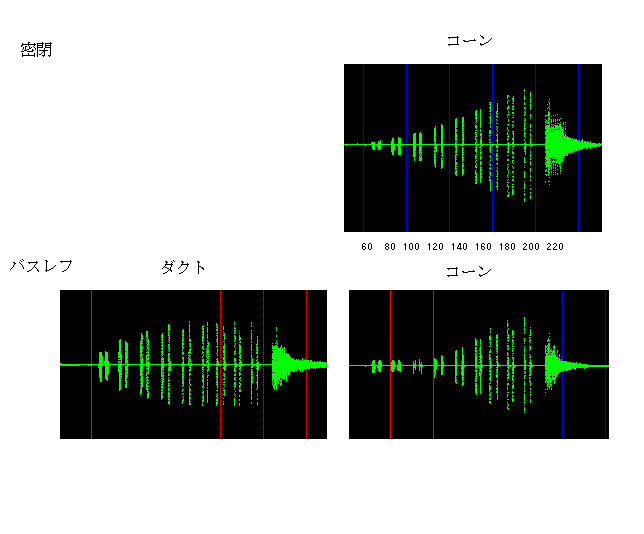
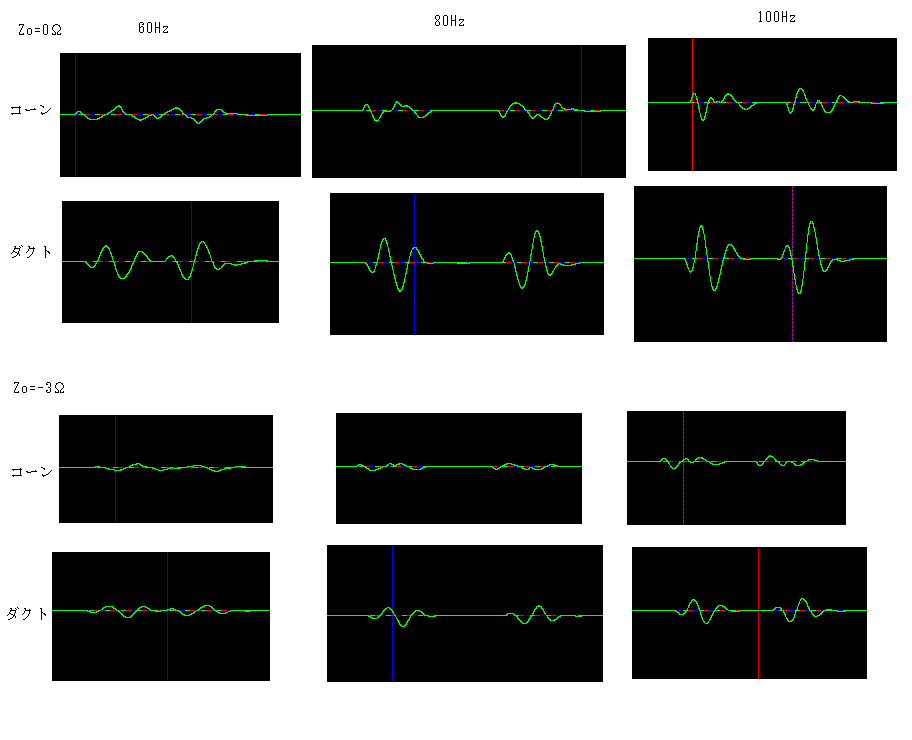
コーンの波形は複雑になっています。おそらくダクト共振による背圧をうけているためでしょう。ダクトが音圧を出している
領域では、コーンはあまり音圧を出していないと考えられます。
ダクトの波形には密閉であったような歪みは認められません。
























































