バスレフの設計は最初にユニットを選び、次に箱の大きさを決めます。
そのときQocが0.57くらいになるようにすると良いと書きましたが、WinIsdで見てみましょう。
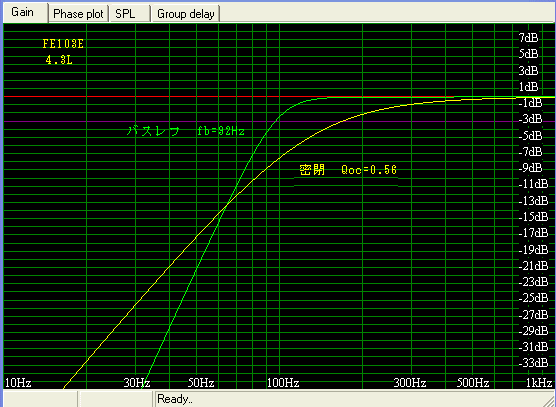
FE103EではQoc=0.56のとき、バスレフでフラットになります。このときQl=7という条件が
つきますがそれについてはあとで見てみましょう。

このようにFF85Kでは0.59となり、どうやらユニットにより若干違ってくるようです。
バスレフのビジュアル的理解
バスレフの設計は最初にユニットを選び、次に箱の大きさを決めます。
そのときQocが0.57くらいになるようにすると良いと書きましたが、WinIsdで見てみましょう。
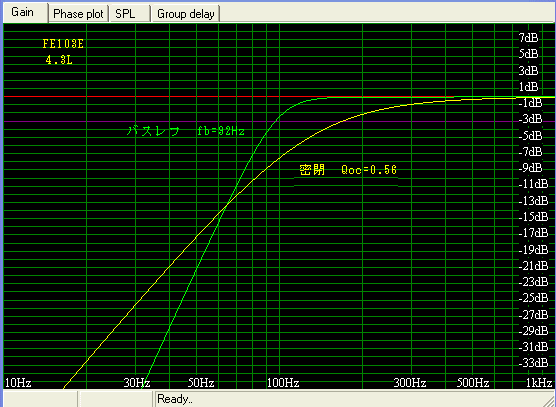
FE103EではQoc=0.56のとき、バスレフでフラットになります。このときQl=7という条件が
つきますがそれについてはあとで見てみましょう。

このようにFF85Kでは0.59となり、どうやらユニットにより若干違ってくるようです。
箱の容積を変化させると、このようになります。

箱が大きいほど、ダクトの音圧は増してゆきます。長岡氏がバスレフをめいっぱい
効かせる為に大型バスレフを設計した理由はここにあります。
同じ箱容積でダクト長を変えてゆくとこうなります。

長くすればするほどfbは低くなりますがどんどんフラットでなくなります。
ダクトの共振のロスを考慮するとこのように変化します。
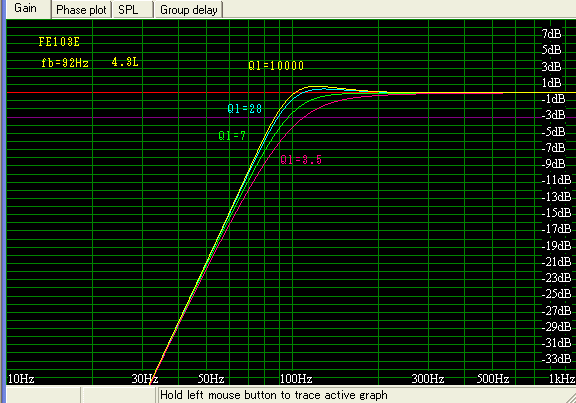
ロスが無いと黄線、多くなれば赤線となります。通常は緑線くらいと見てよいでしょう。
負性インピーダンスアンプでバスレフ駆動すると、このように低域でしゃくれが生じます。
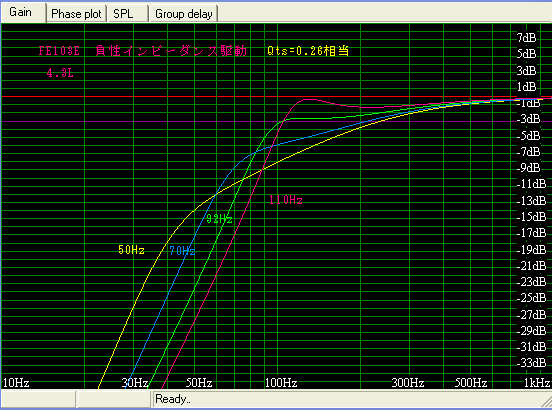
このほうがローブーストしやすいため、少しfbを低めに設定してローブーストする手法が
いわゆるヤマハASTであるといえます。
しかしやろうとすると実際はかなり面倒なので、最初から制動を弱めに設計し、
電流正帰還をかけたときフラットになるような設計法もあります(仮想Qts法)。

図をみていただくとわかるとおり、適正Qtcに設定してあれば、ダクト長を変化させることによって、
フラット特性を得ることができます。ですからカットアンドトライで聴感で決定して成功する可能性は高い
ことになります。一方最初から適正なQtcでない場合はダクトでチューニングしようとしても駄目です。
強力電磁制動アンプでフラットゾーンバスレフを鳴らせば、いままで聴いたことの無いくらい
いい音がするはずです。なぜならそのようなチューニングの製品は滅多に無いからです。
メーカー品ではバスレフの音を嫌い、準密閉としたチューニングが多いと思われます。
そうすると超低域で制動がかかり、コーンのばたつきが防げるので耐入力が上がる利点もあります。
低いチューニング例
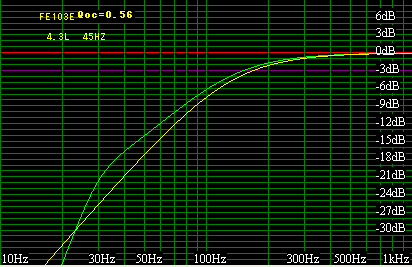
100%バスレフの音を聴いてみたいなら、自分で作って聴いてみるのが早道です。