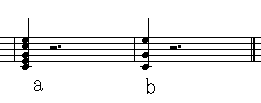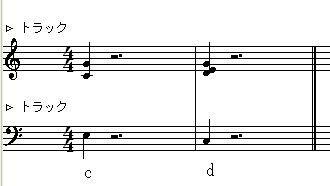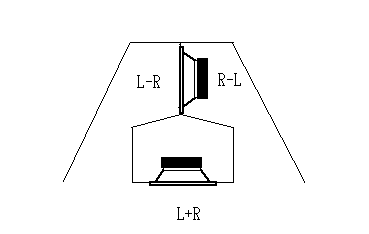FE103講座
第1部 FE103の基礎(2)
| |
用途 |
特徴 |
| BOSE |
PA 店舗
|
・大音量を入れても破綻しにくく、むしろ大音量で真価を発揮する。 ・デッドな屋外でも音が淋しくならないよう間接音を演出。
|
| YAMAHA MSP10
studio
|
スタジオモニター |
・上から下までソースの音をきっちり出す。 |
| FOSTEX FEシリーズ
|
不明 |
・フルレンジなので最高音、最低音はない。
・感度が高いので(ハイコンプライアンス)パワーを入れると歪む。
・ソースの良し悪し、機器の良し悪しをさらけだす。
・条件が揃えば音楽鑑賞にも使える。
|
| Victor
Pioneer
ユーロ等
|
音楽鑑賞 |
・ある程度パワーがはいる。 ・帯域のバランスが良い。
・楽器の音も忠実に再現する。
|
この表は自作をやったり、機器を買ったりしている人なら、だいたい知っていることだと思います。
これを無視すると少々とんちんかんなことになってしまいます。例えば音楽鑑賞用のスピーカー
と比べようとしてFE103に広い部屋でパワーをいれると駄目です。あれは平均入力0.1Wくらいで
使ってやってください。
またあまり知られていない事実ですが、フルレンジスピーカーはアレンジを選ぶのです。たくさんの
楽器が同時に鳴るようなのは苦手で、少ない楽器で音域が近接せずに鳴るというアレンジの曲を得意
にしています。
例
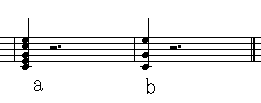
a とbでは述べていることは同じですが、倍音が豊富できれいに響くのはbのほうです。
こういう倍音のひろがりを再現するのが得意なので、選曲も自然にそうなります。
FE103はローコストな10cmフルレンジで歴史は長いですが、今でも秋葉原のショップへ行けば、
一個3000円ちょっとで買うことができます(FE103E)。
ユニットだけでは使えないので、スピーカーボックスも都合しないと駄目ですから普通の人は手を出
したりしません。
手を出すのはどういう理由からかというと、スピーカークラフト入門用としてとか、スピーカーコンテスト
のお題なのでとか、音楽鑑賞用に安くあげたいからとかだと思いますが、長年やっている人の中には
FE103でなければこの音は出せないというところまで到達している人もいるかもしれません。
FE103について一番たくさん書いたり、エンクロージャーを発表したりした人は長岡鉄男氏でしょう。
結論的にはFE103はバスレフが適当、密閉でも悪くはない、バックロードにはFE108シリーズが向いて
いるという感じでしょうか。
長岡鉄男氏は何から何まで作っていますから少々的がしぼりにくいので、私が若干の哲学的考察を加
えてラインアップを考えてみると、
FF85K バスレフ
FE103 バスレフ
FE168Σ バスレフ
FE204 バックロード
が良いかと思います。(バックロードを2つ持つことはできません。)
こうして全部持っておけば、それぞれいつでもテストできますし特徴もだんだんわかってくると思います。
そうするとバックロードは作例をそのまま作るにしても、バスレフについては技術的なことも習熟して
おく必要がありそうです。
マトリックスの衝撃
アンプにも音場感が出るのと出ないのとがあるという衝撃的な記事が出たのは、長岡氏が
FE103を4本使ったマトリックススピーカーをテストに使うようになってからでした。
参考 マトリックススピーカー(フォステクス社製45度タイプ)

概して高級なセパレートアンプでは音場は広がり、中級機との差がでたようです。
その後はスーパースワンにとって替わられましたが、これがアンプのテストにFE103
を使うという思想の萌芽であったわけです。
それ以前はFE203が2発のバックロード+スーパーツイーターでテストしていた
わけですが、これもまた違いをよく識別するシステムでした。
これでテストするとバイポーラアンプとMOS−FETアンプの差が歴然とでるため、
HMA−9500II以後レファレンスアンプがバイポーラに戻ることはありませんでした。
(註:最後はラックスマンだったが経緯は不明)
これらの話はFE203でもおおまかな差はでるが、もっと細密な差まで知るにはFE103
が役に立つということを物語っています。
FE103の最高峰FE103Memorial
線材、接着剤、パルプの処理などにこだわって作られた限定モデルです。それらは音に
反映されています。
完全アンプで聴くこのスピーカーの音は自分で言うのもなんですが、絶品です。
その後工場は台湾へ移され、いまではFE103Eとなり、コーンは木ではなく草の繊維で作ら
れるようになりました。
旧MOSと相性の良いFE103
旧MOSとは、日立の2SK135、2SJ50のシリーズ、東芝の2SK405、2SJ115を言います。
長岡氏が便宜上そう呼んでいただけです。これに対し新MOSにあたるのは東芝2SK1520、2SJ200
のシリーズがそうです。
現行市販アンプでは、サンスイがまだK405で作っているようですが、アンプは高価です。もしFE103
の道を究めるつもりでしたら、入門機としてサンスイのMOS−FETモデルを買っておくことを薦めます。
(FETはまだ地方のパーツショップにはあるようです。)
V−FETアンプの良さを出すFE103
V−FETアンプを最初に作ったときFE203で聴いてみました。確かにK135などのアンプと
くらべて、超細密的な音とふわっとした音が違いとしてあると思いましたが、3台つくった段階で
FE103ペリスコープで聴いてそのすごさに驚きました。
これは代替不可能なレベルだと直感しましたが、実験をくりかえした結果もまさにそのとおり
でした。
V−FETアンプはちょっとやそこらでは手に入りませんから、FE103を極める道は、ますます
狭い道になってゆきます。
パイオニアの8cmに負けるFE103
市販はされてはいませんが、補修パーツとして手に入る8cmフルレンジがあります。
FE103の最大の弱点、振幅がとれないことを、エッジレス構造によりかるく凌駕している
夢のスピーカーですが、若干高域が早く落ちるという欠点があります。
それに目をつむれば、FE族は目ではないくらいのパフォーマンスを示します。特に衝撃音
や、パーカッションを多用したジャズなどで良いです。
ただしASTアンプを使う必要がありますから、これも狭い道のひとつです。
尚、私がFE103を鳴らしているときのパワーはだいたい0.1W、ピークで1W
くらいのものです。
フォスの速度型スピーカーFF125K
Qoがわずか0.25のFF125Kは、ASTなど用いなくともよく制動がかかり、バスレフに
して器楽などを鳴らすと最高です。ということは、簡単すぎて使いこなしの楽しみがないとも
言えます。
FE103だとそこまで行きませんから、電流正帰還をかけたりすることによりQを下げたり
します。またこのように鉄フレーム、フェライト磁石を用いたユニットで多い電流歪みを低減す
るには、若干出力インピーダンスを上げたほうが良いため、アンプ側でQを上げるという手も
ありです。
このようにFE103は実に楽しみ方の多いユニットであると言えます。
万能の天才FE168Σ(あともう少しで)
このバスレフは(又はバックロードは)あと少し高域が伸びていれば、最高の音楽スピーカー
になる素質があります。
欲を出してツイーターを載せてみると全く駄目でしたが、ツイーターなしでも8割方のソースは
こなすことができます。
8cm、10cmだと高域はそんなに苦にしませんが、低域はバスレフに頼りきりですから所詮
サブスピーカーかテスト用スピーカーの運命から脱することはできないのです。
16cmのFE168Σは武蔵野村からきた万能の天才として歴史に残るかもしれません。
音が紙くさいかどうかはアンプ次第です。
和音の続き
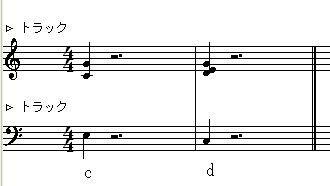
a、bはまじめすぎるためか、いまでは誰もそう書く人はいません。
私的にはcのほうが美しいと思うし、 すこし凝ってみるとdのようになります。
アルニコとフェライト
さらに鉄フレームとアルミダイキャストという問題があり、FE103はどちらも不利といえば
不利です。アルニコ仕様、ダイキャストフレームのFE103の音は如何に?となりますが、残念
ながらそんなのはありません。
BC10はそれに近いわけですが、コーンが違いすぎるのであまり参考にならないようです。
もしこれが破損補修となり、FE103のコーンが張られて帰ってくれば実現することになります。
新マトリックススピーカー
スピーカー2個でできるはずなので、デザインしてみました。L+Rは2個でやるのは少々贅沢な
ので1個ですませたいところですが、いまのところその方法がわかりません。
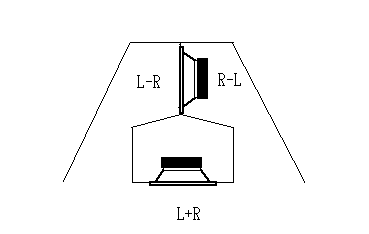
セパレート型マトリックス
こうやって鳴らすと、メインの高域不足をアンビエンスが補ってくれます。正攻法でツイーターを
追加すると音場感が損なわれますから、これはうまい方法です。

視覚的に混乱するためかステレオ感をうまくとらえるには少々慣れが必要です。見ないように
したほうが楽です。
一体型マトリックスはもともとスピーカーの外にも音が拡がりますよというのがウリなので、
コンパクトに作ってサランネットでユニットを隠した方がよいのです。
セパレートなら無理にこうしなくても横一列に並べたほうが、自然な感じになります。