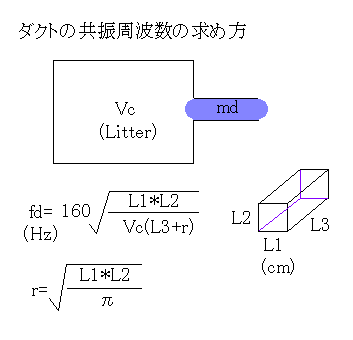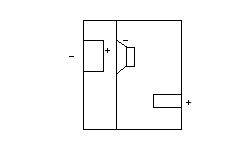バスレフ新研究
はじめに
これまでのバスレフ設計法は自由共振を前提として体系付けられたものであると
いえます。具体的にはユニットによって決まるVs(ユニットの等価換算容積)を基に
して、箱の大きさをQ=0.59?になるように設計し、なおかつユニットのQに最適なfdを
低域最大平坦化条件のもとで決定してゆきます。
これで適度にfo共振が加わり、周波数特性がフラットになる設計が可能になりま
す。
しかしMFBをかける前提で設計するなら、こうした条件は不必要になるといえます。
自由な周波数にfdを設定し、バスレフの音圧レベルもほぼ自由に設定することがで
きます。MFBがかかるとfo共振がほとんど無くなり、入力信号どおりにコーンが動くよ
うになるからです。
負性インピーダンスアンプの入手方法
検出コイルを使わないでMFBをかける方法として負性インピーダンスアンプを用いる
やりかたがあります。理論的には負荷インピーダンスが線形とみなせるときMFBと等価
になります。過去製品化もされてヤマハからAST方式として発売されました。その効果に
驚いた人も多いと思います。
唯一のネックは現在ではASTアンプが手にはいりにくいということでしたが、調べた結果
容易に入手できることがわかりました。パソコンのモニター用スピーカーとしてヤマハから
何種類かでています。低価格ですから気軽に買って実験することができます。
ASTアンプはスピーカーと合わせた専用設計ですが、負性インピーダンスの設定
は安全をみこんで、スピーカーの直流抵抗の半分以下になっていますから、まず大丈
夫といえます。なおYST−M15は4Ω仕様なので、スピーカーが4Ωのほうが出力が
取れます。
MFBアダプターの自作
自作できる人ならMFBアダプターを自作するとアンプの自由度が広がります。手持ちの
アンプにつければ、かなりハイパワーのASTアンプが完成します。
実際に負性インピーダンスかどうかは、測定可能なのでやっておくとよいでしょう。
また検出コイル付きのスピーカーを使えばどのくらいのMFB効果があるかが確認で
きます。
ユニットの選定
直接放射の場合振動板面積で低音の再生限界が制限をうけますが、バスレフ
ダクトの駆動に対しては気圧変化を作ればよいので、小口径でも差し支えありませ
ん。むしろ小口径のほうが同じ圧力を得るのに力が少なくて済みます。
一方バスレフの再生帯域に重ならないようにするために小口径のほうが有利です。
8cmまたは10cmのフルレンジが適当です。
| |
mo |
fo |
Vs |
Qo |
a |
Qm |
| FE83 |
1.15 |
140 |
1.2 |
0.8 |
3 |
4.2 |
| FE103 |
2.7 |
80 |
5.2 |
0.35 |
4 |
2.5 |
| BC10 |
2.2 |
80 |
6.4 |
0.42 |
4 |
2.4 |
| S100 |
3.2 |
80 |
5.3 |
0.43 |
4.2 |
|
| FE108Σ |
2.7 |
80 |
5.2 |
0.28 |
4 |
|
| FE108super |
2.7 |
80 |
5.2 |
0.28 |
4 |
|
| F120A |
4.7 |
65 |
8.0 |
0.45 |
4.6 |
|
| FF125K |
4 |
70 |
8.1 |
0.25 |
4.6 |
|
| FX120 |
5.3 |
65 |
7.0 |
0.46 |
4.6 |
|
| DDDS7 |
9 |
58 |
48 |
1 |
8 |
2.36 |
| 6N-FE88ES |
1.3 |
110 |
1.8 |
0.31 |
3 |
|
| JX-92 |
7.22 |
45 |
10.8 |
0.63 |
4.6 |
|
2
So=スティフネス=(2π*fo)*mo
355*a^4
Vs=ユニットの等価換算容積(l)=---------
fo^2*mo
DCR
Qe=Qm*---------
Rp
Vc/Vs
中音部に対するfobでのレスポンス=-----------
(fd/fo)^2
箱の大きさの決定
いろいろな考え方がありますが、10cmユニットで大きい箱にしても場所をとるだけ
なので小型が望ましいわけです。
FE103の例では表のような作例がありますが、MFBを前提にして作られたわけでは
ないのでかなり大きいものもあります。FE103での低域最大平坦条件を満たす値は、Vc=
3.1L(神野氏の計算による)になりますが、そのような設計例は無いようです。
| |
内寸 |
容積 |
容積減分 |
ダクト径 |
r |
ダクト長 |
L1xL2 |
L3+r |
fd |
| Fostexの推奨箱 |
134x270x171 |
6.150 |
0.3 |
5 |
|
4.5 |
19.625 |
7 |
110 |
| BS3 |
|
6.4 |
0 |
|
3 |
23 |
30 |
26 |
68 |
| カプセル |
|
6.4 |
0 |
|
3 |
7.5 |
28 |
10.5 |
103 |
| 大吟醸 |
(162x122-2100)x300 |
5.2 |
0.3 |
4 |
2 |
5 |
12.5 |
7 |
96 |
| ミニタワー |
126x886x164 |
18 |
0.3 |
4.3 |
2.15 |
14 |
14.5 |
16.65 |
35 |
| FE103ペリスコープ |
|
1.38 |
0.3 |
|
1.78 |
23 |
10 |
24.78 |
97 |
| FE103Mバスレフ |
110x120x170 |
2.24 |
0.18+0.5 |
3 |
1.5 |
6 |
7 |
7.5 |
109 |
| BC10バスレフ(予定) |
149x349x215 |
11.2 |
0.2+0.5 |
3 |
1.5 |
2.5 |
14 |
4 |
92 |
fdの選定
出力インピーダンスが0の電圧出力アンプでは、ボイスコイル加速度特性のピークが
直流抵抗のラインまで抑えこまれますが、MFBではさらにアクティブな制御がなされるこ
とになりますから、foについてはほとんど考慮にいれなくて良いことになります。
fdについても自由ですから、ポートのfdを音圧が欲しい帯域に自由にもってくること
ができるわけです。
したがってポートからの出力を大きくする設計方針になります。
ここが従前と大きく違う点で、いままでは制動感と両立させるため、控えめなダクトチュー
ニングがなされて量感は犠牲にしてもよしという風潮であったと思います。
ポピュラー音楽ではリズムセクション(ベース、ドラム)の帯域をダクトに受け持たせれば
効果的です。その場合fd=50Hzなどとしてはだめで、100〜150Hzというところが適当です。
次にfdの計算式からダクトの大きさを決めます。
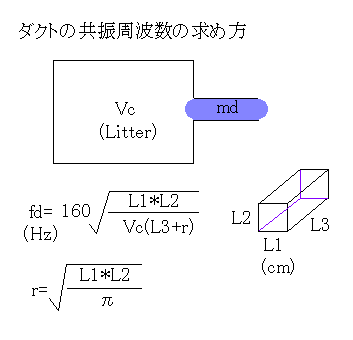
おまけ
ユニットのQoがどのように変わるか。
アンプの出力インピーダンスが−1Ωの場合、Qo=0.35、ユニットの電気インピー
ダンスのfoでのピーク値Rp=50Ω、直流抵抗値DCR=7Ω、ユニットの外部側に直列
につながる抵抗の合計値Rs=-1Ωとすると、
Rp DCR+Rs
50 7-1
Q=Qo*------*-----------=0.35*--------*----=約0.3
Rp+Rs DCR
50-1 7
となるようです。ふつうのユニットでもバックロードのドライブに使うことができる
かもしれません。
スーパーダブルバスレフ

ダクト1からの中高音のもれを最大限利用する。バッフルの共振も
聴こえにくくなるので良いかもしれない。
振動している空気の中を果たして音が抜けてでてくるのか興味深い。
と、ここまで考えたところで根本的にまずいことに気づきました。
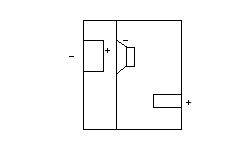
位相で考えると、図のようになり、前面のダクトは逆相になります。
これは没ですね。
ダブルバスレフの原理
一方ダブルバスレフでは、位相は次のようになります。

ダクト1、ダクト2とも共振を生み出す元はスピーカーの
コーンになります。2つのダクト共振は内容積が異なるだけ
で位相は同じです。
その理由は、fd2<<fd1のとき、fd2付近ではダクト1は単なる
空気の通路として働くからです。

このように考えるとわかりやすいと思います。
目次に戻る